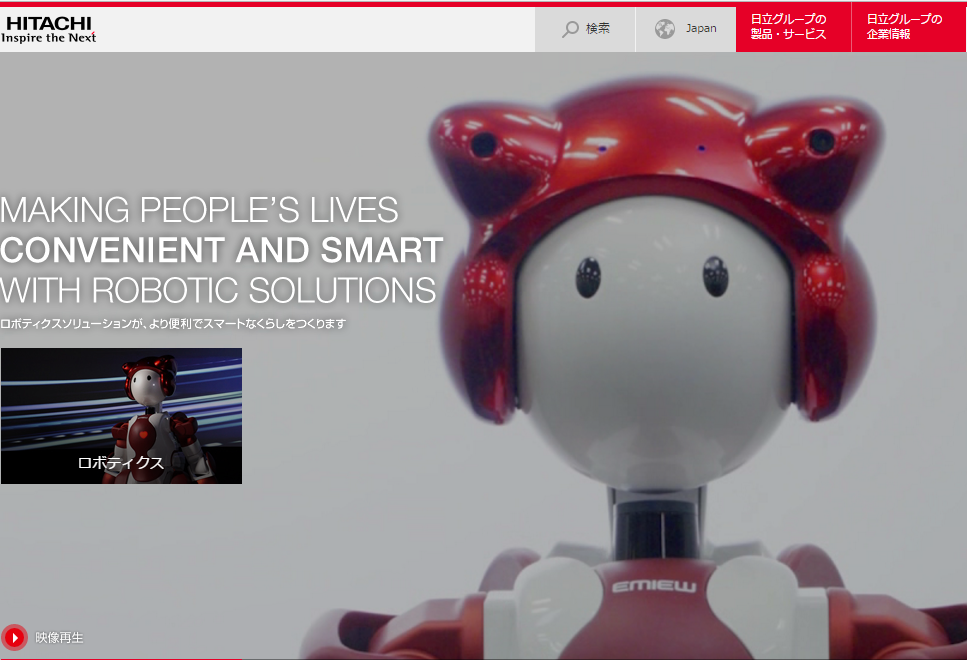- TOP
- >
- 北大と日立、認知症の早期診断を可能にする医療機器開発プロジェクトを受託
新着ニュース30件
2017年1月30日 23:00
早期発見で症状の進行を早期抑制
株式会社日立製作所は2017年1月24日のニュースリリースで、国立大学法人北海道大学とともに、国立研究開発法人日本医療研究開発機溝(AMED)から「認知症の早期診断・早期治療のための医療機器開発プロジェクト」を受託したと発表した。北大と日立は共同で、ハイブリッド撮像・解析法という鉄濃度定量の分布を解析する手法(QSM)と脳の萎縮の程度を客観的に評価する手法(VBM)を組み合わせた画期的な認知症の早期診断、そして検査時間の大幅な短縮が可能となる新たなMRI検査法の研究開発を進めていくとした。研究期間は2016年11月~2019年3月の予定。
ハイブリッド撮像解析法で検査時間も半分に大幅短縮
アルツハイマー型認知症の診療におけるMRI検査は、脳の形態変化から診断に利用し、特に脳の特定部位の萎縮を客観的に評価する手法であるVBMは、軽度認知障害の診断や認知症への移行予測に有用であるが、VBMだけでは認知症の確定が困難なケースがあるため、MRI検査のさらなる開発・発展が必要で、 北海道大学病院では認知症を含めたさまざまな病気のMRI検査法の先端的な臨床研究を行っている。MRI計測の新技術の一つである鉄濃度定量の分布を解析する手法(QSM)は、2011年から日立が開発を推進してきた技術であり、アルツハイマー型認知症での大脳基底核や扁桃体などの特定領域に鉄が沈着して磁化率変化が生じる現象を利用し、VBMの技術と組み合わせて解析することで、軽度認知症段階での診断、認知症への移行予測などにおいて、高い精度の検査が可能になると見込んでいる。
今回の北大と日立により共同研究開発プロジェクトでは、QSMとVBMの同時撮像ができるハイブリッド撮像法を新たに開発し、現状10分以上かかっている撮像時間を5分前後に短縮するほか、QSMとVBMのハイブリッド解析法を開発して、解析時間を大幅に短縮することも目指していく。
(画像は株式会社日立製作所のサイトより)
株式会社日立製作所ニュースリリース
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/01/0124.html
株式会社日立製作所
http://www.hitachi.co.jp/
-->