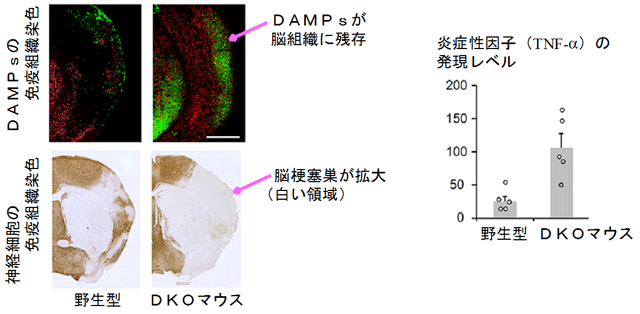- TOP
- >
- 治療法開発に期待。JSTら研究グループ、脳梗塞の炎症収束メカニズムを解明
新着ニュース30件
2017年4月12日 22:00
JSTと慶應、そして筑波が共同研究
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) と慶應義塾大学 医学部、そして筑波大学は、4月11日、脳梗塞の炎症が収束するメカニズムを解明したと発表した。この解明は、JST戦略的創造研究推進事業において、慶應大医学部・七田崇講師らが行ったもの。治療法の開発につながることが期待できる解明だという。
有効な治療法が限られていた脳梗塞
脳梗塞は、寝たきり状態や重篤な後遺症の主な要因となる疾患。発症後に起こる炎症は、脳浮腫や神経症状の悪化の原因となるため、炎症を早く収束させる治療法の開発が期待されている。しかし、炎症収束のメカニズムは未だ解明されておらず、有効な治療法も限られていた。同研究グループは今回、脳梗塞の炎症収束に関わる遺伝子群(Msr1、Marco、Mafb)を発見。壊死した脳組織において産生された炎症惹起因子を、これらの遺伝子群が効率的に排除することを明らかにした。さらに、白血病治療薬「タミバロテン」が、これらの遺伝子群の発現を増加させることも発見している。
治療開始可能時間を広げる治療の開発へ
同研究グループは研究において、脳梗塞を起こしたマウスに対し「タミバロテン」を投与。マウスは、炎症の収束が早まり、神経症状が改善された。同研究グループはこの発見について、脳梗塞発症後における治療開始可能時間を広げる治療の開発につながるものと、期待しているという。
(画像はプレスリリースより)
脳梗塞の炎症が収束するメカニズムを解明 - 国立研究開発法人 科学技術振興機構
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20170411/index.html
-->